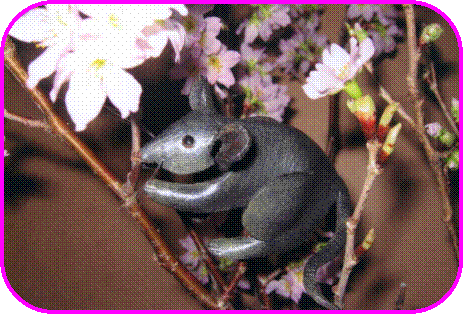 特例民法法人における特例社団法人は行政庁の認定を受けて晴れて公益社団法人となります。 特例民法法人における特例社団法人は行政庁の認定を受けて晴れて公益社団法人となります。
平成20年12月1日より5年間を経過するまでに、公益認定申請書を作成し内閣府公益認定等委員会で認定を受けることになります。5年間は直ぐに経過してしまいます。その間に一度申請し、不認定となれば何度でも申請できますが、審査期間が5〜6ヵ月を要するとなれば多くて申請回数は3回でしょう。
因って研究を重ねて通常考えるより早めに認定申請の手続きをすべきでしょう。
内閣府の公益認定当委員会のホームページを開いて、
右端の「法令関係等」をクリックすると、公益社団法人の
[定款変更案]が画面に現れます。総ページ11ページですので,この定款に準拠して、自社の旧定款を並べて自社の定款を作成します。
旧特例民法法人の定款は永い歴史の中で育まれたもので
それなりに価値のあるものですが、認定法及び一般法人法に基づく定款でなくてはなりませんので、出来る限り独自性は出さない[定款変更案]に添ったものにすると認定が早期におります。
定款には必要的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がありますが、「定款変更案」では__又は‥‥で表示しています。
社員の定め方、会費の定め方、理事の選任方法、監事の
選任等 注意点がありますが、わからなくなったときは
新会社法の考え方が公益法人の定款にも影響していることを考えますと理解が早くなります。
「定款変更案の作成案内」(見開き印刷用)を見ると大変良く理解できます。同じ関係法令等の直ぐ上に記載されています。
申請書様式ももダウンロードして書いてみますと、定款の目的、事業の条文も実際の事業運営と一致してきます。
以上ですが、各都道府県でも相談に毎月応じていますの
で公益認定等委員会のホ−ムページへ申し込んで下さい。
親切に相談に応じて頂けます。
家内が作成した革工芸のネズミです。 |

